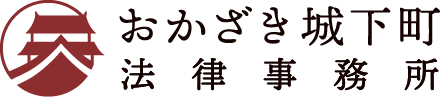ご相談事例
教職員の残業代請求の可否について
国立大付属校の教職員に対して本来支払われるべき残業代が支給されていなかったとして、約4割の国立大学法人が労基署から是正勧告や指導を受けていたそうです(R4.2.22毎日夕刊)。未払残業代があった教員は2952人に上り、過去2年分に遡ってすでに計15億円以上が支払われたとのこと。
公立学校の教職員に対しては、教職員給与特別措置法(給特法)という特別法により、月額給与の4%を教職調整額として上乗せされています。これによって、割増賃金の根拠規定となっている労基法37条の適用が排除されていることから、一般に公立学校の教職員には残業代を支払わなくてもいいと考えられがちなのですが、国立大付属校の教職員については国立大学が独立行政法人化されたときに給特法の適用対象から外れていたようです。
このニュースに関連して思い出したのが、給特法の適用を受ける公立小学校の教員が県に対して残業代等の支払いを請求した事件(さいたま地裁令和3年10月1日判決)。この裁判で、原告(教員)側は、労基法37条に基づく割増賃金の請求の他に同法32条の定める労働時間を超えて労働させることが国家賠償法上違法であるとも主張していました。結論としては、2つの請求とも棄却されていますが、裁判所(合議体)は判決文の最後で「現在の我が国における教育現場の実情としては、多くの教育職員が、学校長の職務命令などから一定の時間外勤務に従事せざるを得ない状況にあり、給料月額4パーセントの割合による教職調整額の支給を定めた給特法は、もはや教育現場の実情に適合していないのではないかとの思いを抱かざるを得ず、原告が本件訴訟を通じて、この問題を社会に提議したことは意義があるものと考える。」と付言しています。
昨今の教育現場をとりまく環境や世論をみていると、一般の公立学校の教職員についても、早晩、労働時間を正確に把握した上でそこから通常の割増賃金を支払う制度に切り替わるのではないでしょうか。