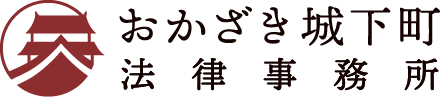ご相談事例
賃貸借か使用貸借か悩ましい事案
昨年、不動産明渡事件の依頼を5件受けました(3件は解決済、2件は裁判係属中)。そのうちの1件が、依頼者の祖父の代から土地(住宅用)を貸していて契約書はなし、土地を貸した当時の状況はまったく不明、現在受け取っている地代は年間4万円(固定資産税とほぼ同額)という特殊な事案で、依頼者としては土地を所有していてもまったく有効利用できないので、早急に建物を取り壊して土地を明け渡して欲しいという考えをもっていました。
この契約関係が、仮に賃貸借契約だとすれば、明渡しを求める正当事由がない限り契約は法定更新されていきますので、土地の明け渡しの請求は困難となります。しかし、これが使用貸借契約であるならば、改正前民法では「当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる」(597条3項)と規定されていましたので、この規定により返還請求が可能となります。そこで問題は、年間4万円が土地利用の対価=「有償」と評価できるかどうか。この点、過去の最高裁判例では、「建物の借主がその建物等につき賦課される公租公課を負担しても、それが使用収益に対する対価の意味をもつものと認めるに足りる特別の事情のないかぎり、この負担は借主の貸主に対する関係を使用貸借と認める妨げとなるものではない。」との判断が示されています(最判昭和41年10月27日判決)。私が依頼を受けた案件も、固定資産税とほぼ同額の金銭しか受け取っていなかったことから、この判例を前提に使用貸借契約と判断して交渉を進めていきました。
相手方の借主としては、今まで50年以上怠ることなく地代を支払ってきたので納得がいかないという姿勢を崩さなかったため、最終的には、双方が譲歩して、借主が相場よりも低い金額で土地を買い取ることにより事件は決着しました。この件では話し合いにより早期解決となりましたが、もし裁判になったらどのような認定がされたのか、民法の法解釈として興味深い案件だったと思います。
弁護士 市村陽平