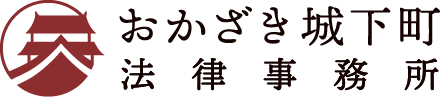ご相談事例
変形労働時間制について
日頃、企業から相談や依頼を受ける労働紛争の中で、解雇と並んで件数が多いのが、従業員からの残業代請求です。この残業代請求に対しては、従業員の主張する労働時間性自体を争ったり、定額手当の支給を主張することなどが企業の反論手段になるわけですが、稀に変形労働時間制の適用を主張するケースもあります。
変形労働時間制とは、ある特定の日や週の労働時間が法定の上限を超えることがあっても、1か月や1年を単位とする一定期間の平均労働時間が法定労働時間を超えなければ労基法32条違反とならない制度です。しかし、私の感覚からすると、裁判で企業側からの変形労働時間制の主張が認められる事案はかなり少なく、使用者が想像している以上にハードルが高いのではないかという認識をもっています。そもそも、裁判等で変形労働時間制を主張するためには、就業規則または就業規則に準ずる書面において、①労働時間の総枠の定め、②変形期間における労働時間の特定、③変形期間の起算日を明示していなければなりません。さらに、過去の最高裁の判例や行政解釈では、以上の要件に加えて、変形期間における各日、各週の労働時間(始業・終業時刻)まで明示する必要があるとされています。この点、企業が使用する標準的な就業規則には、一応の規定として変形労働時間制の定めもありますが、通常は、当該企業固有の労働パターンまでは具体的に書き込まれていませんので、単にモデル就業規則をそのまま用いているだけでは裁判所に一蹴される結果となってしまいます。
また、就業規則にある程度具体的に労働パターンが設定されている企業でも、現在の勤務ローテーションが就業規則作成時から変更されていて、両者の間に齟齬が生じているというケースも見受けられます。これまでの裁判例の傾向からすると、変形労働時間制の適用に関して、裁判所は非常に厳しく要件を見ていますので、この場合、就業規則が無効と判断されるリスクが高いといえます。したがって、平時から就業規則の内容と実際の従業員の勤務シフトが適合しているかの確認も怠らないようにする必要があります。
訴訟で争った結果、最終的に企業側の変形労働時間制の主張が認められなかったらどうなってしまうのでしょうか。近時の裁判例では、1日8時間を超えた労働時間はすべて時間外労働となり、この部分に関してはまったく賃金が支払われていないとして全額の割増賃金の支払いを命じた判決もありました。そうなると、使用者側にとっては一か八かの非常にリスキーな争いになってきますので、訴訟になった際には、変形労働時間制の攻防だけに終始しないよう気をつける必要があるでしょう。
弁護士 市村陽平