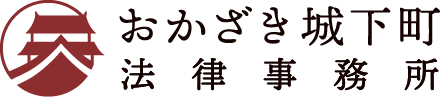ご相談事例
従業員に自宅待機を命じる際の留意点
会社が従業員に対して指揮命令や処分をする際、手続の意味を正確に理解していないと揚げ足をとられてしまうケースが少なくありません。先日も、ある会社で従業員がパワハラ行為を繰り返すので、自宅待機をさせたいという相談がありました。このとき、上司2名が相談にきたのですが、よくよく話しを聞いてみると、そのうちの一人は懲戒処分としての自宅待機命令(出勤停止)を想定していたのに対し、もう一人は社内調査するための期間自宅待機をさせたいと考えていたようです。
両者が考えるこの二つの方法は、似ているようで法的な手続としては大きく意味が異なります。まず、命令する根拠の有無ですが、後者の場合であれば、通常の業務命令として自宅待機を命じることができ就業規則の根拠は必要になりませんが、前者の懲戒処分として行う自宅待機であれば就業規則上の根拠が必要となります。また、自宅待機中の賃金発生の有無についても考え方が異なってきます。後者は、あくまで会社都合による労務提供の受領拒否と捉えられるため、待機期間中は賃金を全額支払うことが基本となります(民法536条2項)。もっとも、民法の特別法に位置づけられる労働基準法26条に基づいて、就業規則で平均賃金の60%の保障を定めて民法の規定を排除することは可能です。他方、懲戒処分として自宅待機を命じる場合には、制裁としての出勤停止の当然の帰結であると考えられていることから、賃金請求権は発生せず、その間は勤続年数にも通算されません。
この他にも、いったん前者の判断をした後、社内調査を経て、同様の理由で懲戒解雇をするなどした場合には、二重処罰にも該当してしまいます。法律の世界では、似たような効果をもたらす手続や処分でも制度趣旨や要件が異なるといったことはよくありますので、会社として意思決定をする場面では、就業規則に照らして正確な判断が求められます。
弁護士 市村陽平