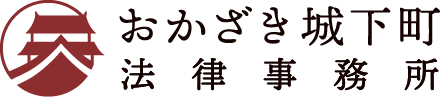ご相談事例
労働者の「自由な意思」論について
通常、人が物を売ったり買ったりする場合には、当事者の口頭での合意や、契約書を取り交わす形の合意で、有効に効力が発生します。これは、どの業界・分野でも至極当然のことだと思われますが、実は、労働法の世界ではそうではありません。
近年の傾向として、労働者が賃金の減額や、配転、降格等の労働条件変更にいったん合意しても、後々、裁判等で「自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在しない」として、合意が無効とされる事案が増えてきています。
使用者としては、本人の意見も聞いた上で慎重に書面で合意を取り交わしても、労働者の「自由な意思」ではないとして、後々の裁判で効力がひっくり返されてしまうのですから、まさに青天の霹靂です。たとえ、条件変更する理由が、会社の合併等の経営上の必要性であったり、職員の産休育休に伴う人事上の必要性であっても、裁判所はあまり取り合ってくれません。
このように、事後の予測可能性が見通しにくい中で、使用者はどのようにして労働者と合意をしていけばいいのでしょうか。確実な方法というのはありませんが、①労働者に生じる不利益の内容や程度を抑制する、②合意を取り交わす手続面として、会社の説明の機会や本人の意向確認の機会を複数回設定する、③即座に労働者の回答を求めるのではなく、持ち帰って検討する時間的猶予を与える、といった対応が重要になります。
労働者の「自由な意思」という中身のよくわからない理論に依拠する近年の労働判例を見る度に、改めて、社会常識が通用しない特殊な世界だなと実感する次第です。
弁護士 市村陽平